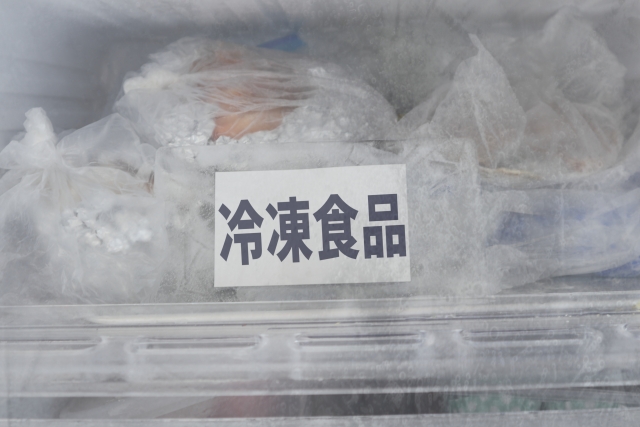近年、冷凍食品の需要が増加する一方で、価格の上昇が続いています。家庭用・業務用を問わず、さまざまな冷凍食品が値上がりしており、消費者や飲食業界にとって大きな影響を与えています。本記事では、冷凍食品の値上がりの現状とその背景、さらに今後の見通しについて詳しく解説します。
目次
- 冷凍食品の値上がりの現状
- 価格上昇の主な要因
- 冷凍食品市場の今後の動向
- 消費者や飲食店がとるべき対策
- まとめ
1. 冷凍食品の値上がりの現状
近年、冷凍食品の価格は着実に上昇しています。家庭用の冷凍食品では、冷凍野菜や冷凍麺類、冷凍惣菜などの価格が上がっており、スーパーやコンビニの販売価格にも影響を与えています。また、飲食店向けの業務用冷凍食品も同様に値上がりしており、特に原材料の高騰が影響していることが指摘されています。この価格上昇の傾向は、コロナ禍以降さらに加速しており、消費者や企業のコスト負担が増しているのが現状です。
2. 価格上昇の主な要因
冷凍食品の価格が上がる背景には、さまざまな要因があります。まず、世界的な原材料価格の高騰が挙げられます。小麦粉や食用油、肉類などの食材の価格が上昇しており、それが冷凍食品の製造コストに影響を及ぼしています。また、エネルギー価格の上昇も大きな要因です。冷凍食品の製造には大量の電力や冷媒が必要であり、電気代や燃料費の高騰が価格に反映されています。さらに、物流コストの増加も重要な要素です。国際的な輸送費の上昇や国内の人手不足による物流費の増加が、冷凍食品の価格を押し上げる要因となっています。
3. 冷凍食品市場の今後の動向
今後の冷凍食品市場は、引き続き価格上昇の傾向が続く可能性があります。特に、原材料価格やエネルギーコストが大きな要因となるため、それらの動向次第でさらに値上がりすることも考えられます。ただし、冷凍技術の進化や生産効率の向上によって、一定の価格安定が図られる可能性もあります。また、環境負荷の低減を目指したサステナブルな冷凍食品の開発が進んでおり、代替原料を活用した新しい商品が登場することで、価格面での変化が生まれる可能性もあります。
4. 消費者や飲食店がとるべき対策
冷凍食品の価格上昇に対して、消費者や飲食店ができる対策はいくつかあります。家庭では、特売日を活用してまとめ買いをする、安定供給されている食材を活用した冷凍食品を選ぶといった方法があります。一方、飲食店では、仕入れ先の見直しや業務用冷凍食品の活用、冷凍食品と生鮮食品のバランスを見極めたメニュー構成などが求められます。また、業務用の冷凍庫を活用し、仕入れた食材を長期保存することで、コストを抑える工夫も重要です。
5. まとめ
冷凍食品の値上がりは、原材料費やエネルギーコスト、物流費の高騰など複数の要因が影響しています。今後もこの傾向は続く可能性が高く、消費者や飲食業界にとって負担が増すことが予想されます。しかし、冷凍技術の進化や代替原料の活用など、価格を安定させる動きも出てきています。消費者や飲食店は、賢く冷凍食品を選び、コスト管理をしながら活用していくことが求められます。
菅野製麺所の皮類製造現場は、全国製麺協同組合連合会のHACCP高度化計画の認定を受けていますので、安心して召し上がっていただけます。餃子やシュウマイ、肉まん、あんまんなどの点心を家庭の食卓で楽しめます。こだわりぬいた食材と製法で作られたひと味違う点心をぜひご賞味ください。
株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。
公式サイト